技術開発には常に難関が立ちはだかる。
特に今まで誰も踏み入れたことの無い世界ほどその度合が大きい。
時には技術的な絶望感に陥ることさえある。しかしこれは何としてでも避けねばならぬ。
何事にも手詰まりということはない、必ずどこかに攻め手があると考える態度が必要だと思う。
私のポストは研究部長である。いわば一般的には管理職である。
しかし単なる管理職的な格好で研究部長の椅子にすわっていたのでは私の役は務まらない。
私自身もつぎつぎと攻め手を示していく必要があった。私自身現役の技術者に戻ることにした。
自分でも考え、計算し、図面を描き実験し…いわゆるプレイングマネジャーである。
私のアイデアが必ずしも上手く行くとは限らない、むしろ失敗することの方が多かった。しかしその失敗の中から新しいアイデアが出た。
失敗を恐れるなということを常に部員の心に植えつけると共に、私自身も態度で示した。
ロータリーエンジン実用化開発の初期、われわれの前に立ちはだかった最大の難関は、
例のチャターマークであった。
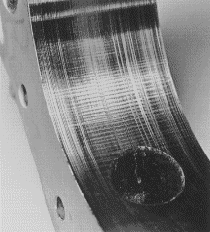 ローターの三つの項点シールが常にまゆ型のローターハウジングの内面に密着し、その壁面をこすりながら、ものすごい速度でまわる訳である。ハウジングの内面は硬質のクロームメッキがほどこされているが、数時間の運転でその表面がガタガタになる。初め鏡の様な表面がまるで洗濯板の様になってしまう。
ローターの三つの項点シールが常にまゆ型のローターハウジングの内面に密着し、その壁面をこすりながら、ものすごい速度でまわる訳である。ハウジングの内面は硬質のクロームメッキがほどこされているが、数時間の運転でその表面がガタガタになる。初め鏡の様な表面がまるで洗濯板の様になってしまう。
ありとあらゆる材料が試みられた。金や銀を含有した金属、果ては牛の骨までも試してみた。
また、シールの形状にも種々のアイデアを盛り込んだ。チャターマーク発生メカニズム解明の為に新しい振動計測法も開発された。しかし研究室にはチャターマークで無残な姿のローターハウジングが山積になるばかりであった。
昭和 38年の秋、チャターマーク発生のメカニズムを研究していたグループから頂点シールの形状を工夫し周波数特性を変えてみてはというアイデアが出された。
金属シールの先端近くにヨコ孔をあけ、さらにこれと交差してタテ孔をあけた。
クロスホロー(cross hollow)と呼ばれるこのシールの成果を固唾をのみながら見守る一同の前でテスト後のエンジンが分解されて
いく。
一瞬の沈黙がやがて歓声へと変わった。あの悪魔の爪跡、チャターマークがなくなっていた。
今でも私は、苦難のロータリーエンジン開発史の中での輝かしい一瞬であったと思う。

技術的に一つの壁を乗り越え、翌昭和 39年の初め、NSU訪問時の手土産に、この成果を報告し、彼等をして、驚きと称賛を言わしめたというだけではない。
1960年代から 1970年の初めにかけて、日本の技術は「追いつけ追い越せ」とばかりに目ざましい発展をとげていた。
しかし先を行く欧米諸国の技術を改善し、たしかに器用に独特の味をつけてはいくが、模倣と言われても仕方がない体質があった。
我々のロータリーエンジンの開発でさえ、先例のない、サンプルのないものへの挑戦であったにもかかわらず一足先を走る NSU社はどうだろうか、カーチスライト社はどの様に考えているのだろうか等、気にしていた。
新しい物、特に挑戦的な物へ取組んでいく為には、こうした日本の従来の技術風土を打破って行く必要がある。種々の技術を参考にするのは良い、また同じ苦労をする世界中の技術者が自らの意見を闘わし、研鑚していくのは大いに結構な事である。
しかしながら人の後ろを安全にトレースするといった態度では決して挑戦的なものは生まれない。
その後、このシールは金属からカーボンに変えられ、量産のロータリーエンジン 1号車はカーボンシールでデビューすることになる。
つまりクロスホローは世の中には出なかったが、新しい物の考え方、模倣でなく技術者が自らの力で自信を持って問題解決に挑戦するという、風土を確立するための大きな出来事であったと思う。
つまり日本の技術者の従来のマインドスタイルへの挑戦でもあったと思う。この様な風土が数々の独特の技術を生み、エンジンの機構や部品はもとより、新しい計測法や生産技術へと挑戦して行く大きな原動力となったことは言うまでもない。
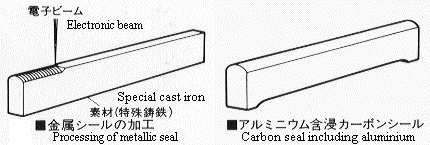
やがて、この頂点シールはカーボンから再び金属になり現在に至っている。性能や燃費の為のガスシール性能向上の為、カーボンでは出来ない複雑さや、精度などを要求されたのも理由であるが、カーボンでは飽き足らずやはり金属でと考えた技術者の信念が、その後電子ビーム法によるシールトップ面のチル化を成功させたことも大きく寄与していることをつけ加えておきたい。





